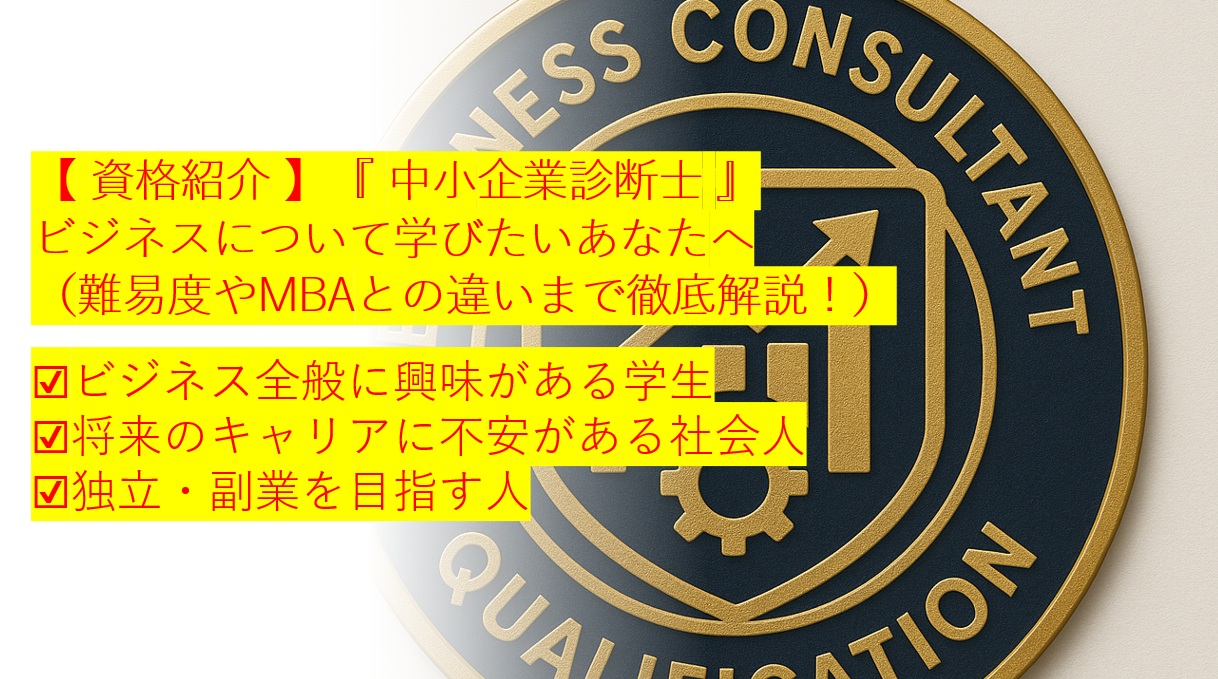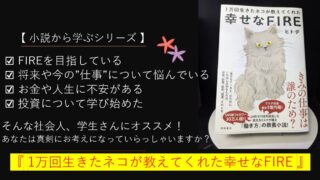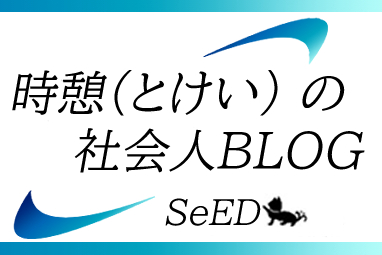時憩(とけい)です!
みなさんは、”MBA”をご存じでしょうか?
Master of Business Administration (マスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーション)
…つまりビジネスを経営するための学問である「経営学」をおさめた人に与えられる称号のようなものですね。
簡単にまとめると、以下のようなことを学びます。
| 項目 | 内容 |
| ①ビジネスのやり方 | どうやって会社を運営し、成功させるために必要な方法を学び |
| ②商品の売り方 | どうすればお客さんに商品を買ってもらえるか、売り方や広告の方法について学び |
| ③お金の使い方 | 会社のお金の管理や、どうやって悪お金を集めるかを学び |
| ④チームのまとめ方 | どうリーダーシップをとるか、チームを上手くまとめる方法を学ぶ |
なんかMBAって響きが、カッコいいですよね!
内容も将来のことを考えると、取っておいて損は無さそうです。
MBAは「ヒト・モノ・カネ」に関連する企業経営に必要な知識を体系的に学んだことを証明できるアメリカ発祥の”学位”ですが、日本のMBAと言われている”資格”があります。
それが今回紹介したい『 中小企業診断士 』!
知っておきたい『MBAと中小企業診断士の違いと要約』
まず初めに『MBAと中小企業診断士の違い』と『要約』を
それぞれの簡単にまとめてみました。
| 項目 | MBA(経営学修士) | 中小企業診断士 |
| 対象者 | ビジネスのリーダーや経営者を目指す人、またはキャリアアップを狙う社会人。 | 中小企業の経営者や経営コンサルタントを目指す人。 |
| 目的 | ビジネス全般に関する高度な知識を学び、リーダーシップを発揮することを目的とする。(将来の経営者・経営幹部の育成) | 中小企業の経営支援やコンサルティングを行うことを目的とする。 |
| 主な内容 | 【ケーススタディが中心】 経営戦略、マーケティング、ファイナンス、リーダーシップ、組織論など。 ①経営戦略・マーケティング・オペレーション ②組織・人的資源・リーダーシップ ③会計・財務分析 ④経営数理・経営思想 ⑤グローバルビジネス 他 | 【知識やスキルの取得】 中小企業の経営改善、経営戦略、マーケティング、財務分析など。 ①経営学・経営政策 ②財務・会計 ③企業経営理論 ④運営管理 ⑤経営法務 ⑥経営情報システム ⑦中小企業経営・政策 |
| 取得後の役割 | 大企業やスタートアップの経営、経営戦略の立案、経営全般に関わる仕事。 | 中小企業の経営相談、経営コンサルタント、企業の改善支援。 |
| 取得方法 | 大学院で経営学を学び、学位(修士)を取得することで得られる。 (単位取得および修士論文_専門職学位論文を提出) | 資格試験に合格し、 実務補習または実務経験を積むことで取得。 |
| 費用 | 200万円~ | 10~40万程度(学習形態による) |
| 取得までの期間 | 通常、2年程度の大学院で学んだ後に修士号を取得。 | 6か月~1,2年程度の試験勉強。 試験合格後、実務経験を積むことが必要。 |
| 学位 / 資格 | 学位(修士号) | 資格(国家資格) |
つまり、両方とも取得を目指す中で、
経営・ビジネス全般の知識を体系的に広く学ぶことができるが、
目的や取得方法、費用などが異なっていることになりますね。
続いて、要約した中小企業診断士の内容について、項目別により深く見ていきましょう!
どんな人におすすめなの?
『中小企業診断士』を取得するにあたり、オススメする人は以下のような人たちです。
①ビジネス全般に興味がある学生
「ビジネスの仕組みを学んで、将来に備えたい!」
「世の中をよりよくするために、論理的に物事を考えられるようになりたい。」
②将来のキャリアに不安がある社会人
「営業を行う上で、営業相手の会社状況を理解したうえでの提案を行えるようになりたい」
「もっとスキルアップして、社内での地位や信頼を高めたい!」
「このまま今の会社で働き続けていいのだろうか…」
③独立・副業を目指す人
「独立して、会社の社長になりたい!」
「ほかの資格やスキルと組み合わせて、副業したい。」
そんなことを考えている方にとって『中小企業診断士』は、経営、財務、マーケティングなどビジネスの基礎から応用まで体系的に学べるので、
汎用性の高いスキルが身につき、仕事で使える知識と論理的な思考力が身につく
ピッタリの資格です!
中小企業診断士って具体的にどんなことをするの?
「中小企業診断士って、“経営コンサルタントの国家資格”って聞いたけど、実際には何するの?」
そんな疑問を持つ方のために、ここでは診断士の主な活動内容をご紹介します。
| 働き方 | 具体例 |
| 独立 _ 診断士 | フリーのコンサル、講師、執筆活動など |
| 企業内 _ 診断士 | 社内で経営企画・改善プロジェクトに関与 |
| 副業 _ 診断士 | 本業を続けつつ、土日に補助金支援やセミナー講師 |
具体的には以下のような業務などがあります。
①企業への経営診断・アドバイス
企業の現状を分析し、課題を見つけ、改善策を提案する。
例えば、
●売上が伸び悩んでいる → 市場・競合分析し、販売戦略を見直す
●在庫が過剰 → 生産・物流体制を分析し、改善提案
●人手不足 → 組織体制や人材育成の仕組みを再設計
など中小企業経営者と対話しながら、実際の現場課題を一緒に解決していきます。
②補助金・助成金の申請支援
中小企業にとって、国や自治体の補助金はとても大切な資金源になります。
診断士は、事業再構築補助金、ものづくり補助金などの申請書作成をサポートすることが多くなります。
●補助金制度を説明
●計画書(ビジネスプラン)を一緒に作成
●採択されるためのアドバイス
なお、この分野でのニーズは非常に高く、副業や独立の収入源にもなります。
③創業・起業の支援
起業希望者に対して、事業計画の立て方や資金調達のアドバイスをする仕事。
創業塾や商工会議所でのセミナー講師としても活躍できます。
例えば、
「カフェを始めたいけど、開業にどれくらい資金が必要か分からない」
といった人がいた時に、初期投資、損益分岐点、集客戦略などを一緒に考えるなど。
④公的機関での支援業務
中小企業診断士は、中小企業支援センター、商工会議所、地方自治体などで相談員として働くこともあります。
●経営に困っている企業の無料相談対応
●経営改善計画の作成支援
●各種セミナーや勉強会の講師
⑤社内コンサル・経営企画として活躍
企業勤務の方も、診断士の知識を活かして経営企画部、事業開発、商品戦略などで活躍します。
●市場調査
●経営計画の策定
●M&Aや新規事業の評価・推進
会社の中で「経営視点で動ける人材」として重宝されます。
取得するメリット
①経営の総合力が身につく
中小企業診断士の学習範囲は、経営戦略・財務・人事・マーケティング・生産管理・法務・ITなど多岐にわたります。
つまり、ビジネスの“全体像”が見えるようになり、どんな職種でも一段上の視点で仕事ができるようになる、「会社をどう動かすか」を広く・体系的に学べる国家資格です
②キャリアアップ・昇進につながる
診断士は「経営のわかる人材」として評価されやすく、次のようなポジションを目指しやすくなります。
●経営企画部門
●新規事業開発
●管理職(課長・部長など)
●組織改革・改善プロジェクトのリーダー
私が普段働いている会社では、管理職になるために必要な選択資格の1つになっていますね。
③独立・副業の道が開ける
診断士は、コンサルタントとして独立開業が可能な数少ない国家資格の一つ。補助金支援や創業支援、セミナー講師など、個人で収入を得られる仕事も多いです。
「会社に頼らない働き方をしたい」「副業で収入を増やしたい」人に最適ですね!
④信頼性が高く、公的機関や士業と連携しやすい
診断士は経済産業省が認定する国家資格のため、公的支援機関(商工会議所・よろず支援拠点など)での活動や他士業(税理士・社労士など)との連携がしやすいのが特徴。
●公的な相談員業務
●他士業とのジョイントワーク(補助金申請など)
⑤診断士は「人とつながる資格」
中小企業診断士は資格取得後、
独立している診断士同士が仕事を紹介し合ったり、協業したりすることも多く、
診断士同士は「仲間意識」が強く、“横のつながり(ネットワーク)”が非常に強いことで知られる資格です。
また都道府県ごとにある中小企業診断協会に登録することで、さまざまなネットワークに参加できます。
●地域の診断士との情報交換
●研究会や勉強会(マーケティング、DX、海外進出などテーマ別)
●公的機関からの仕事(補助金支援、経営相談など)の紹介
中小企業診断士は、単なる肩書き以上に。
『実践に活きる知識』と、『仲間』をくれます。
企業に勤めながらキャリアを切り拓くもよし、副業・独立で活かすもよしの資格です。
資格試験(資格取得)の流れ
ステップ①:一次試験(マーク式)
●毎年8月頃に実施(2日間)
●合格率は約20%前後(年によって変動)
●一部合格制度あり(合格科目は2年間有効)
まずは7科目の筆記試験(選択式)。経営に関わる幅広い知識が問われます。
| 科目 | 内容 |
| 経済学・経済政策 | マクロ・ミクロ経済 |
| 財務・会計 | 損益計算書、貸借対照表、原価計算など |
| 企業経営理論 | 組織論、マーケティング、戦略 |
| 運営管理 | 生産管理、店舗・物流管理 |
| 経営法務 | 商法、会社法、知的財産権など |
| 経営情報システム | IT基礎、情報管理 |
| 中小企業経営・政策 | 中小企業の支援策や実態 |
ステップ②:二次試験(一次試験合格者のみが受験可能。)
●筆記試験は10月、口述は12月
●合格率は筆記で約18%前後、口述はほぼ全員合格
一次試験合格者のみが受験可能。
| 試験に内容 | 概要 |
| 筆記試験(4科目) | 組織・マーケ・財務・運営に関する事例分析と提案 |
| ↓ ↓ 口述試験(面接形式) | 筆記試験合格者対象、 プレゼン・対話力を確認 |
ステップ③:実務補習 or 実務従事
二次試験合格後は、「実務経験(15日分)」が必要です。
方法①:実務補習(診断協会の研修)
→指導員付きの企業診断をチームで行う
5日コース×3回で計15日を満たせる
費用:約20万円前後
方法②:実務従事(自分で企業支援を行う)
→企業診断・補助金支援・経営相談などで実績を積む
指導者不要だが、証明書類が必要
ステップ④:中小企業診断士として登録
実務を終えたら、中小企業庁に登録申請(登録後「中小企業診断士」の名乗りが可能に)
●登録費用:約3万円前後(+更新は5年ごと)
勉強方法・おすすめの教材
資格取得まで、勉強時間1,000〜1,200時間、
社会人なら1.5〜2年が一般的です。
しっかり計画すれば独学でも合格可能ですので、継続していきましょう!
① おすすめの勉強法(一次・二次それぞれ)
📝 一次試験の勉強法
- 【インプット】通信講座 or 独学テキストで知識を固める
- 【アウトプット】過去問5年分+模試を必ず解く
- 【時間配分】7科目あるので、苦手を早めに見極めて重点配分
📌 ポイント:
一次は「広く浅く+暗記力」勝負!
スキマ時間を有効に活用しよう(通勤中の音声学習も◎)
✍️ 二次試験の勉強法
- 【過去問演習】過去10年分を繰り返し解く
- 【答案練習】フレームワークで書き方を型にする
- 【添削】予備校・勉強会で第三者に見てもらうのが重要!
📌 ポイント:
二次は「日本語で論理的に書く力」が問われるため、独学より“添削・対話”が重要!
② 勉強スタイル別:おすすめ学習法
| タイプ | おすすめ |
|---|---|
| 完全独学 | TACスピードテキスト+過去問+YouTube |
| 通信講座派 | スタディング、クレアール、TAC通信など |
| 通学派 | 大手予備校(TAC、大原、LECなど)で講義+添削指導 |
よくある疑問Q&A
Q1. 中小企業診断士って文系でも受かりますか?
A. はい、文系出身でも十分合格できます。
実際、合格者には文系の方も多数います。
一次試験には「財務・会計」や「経済学」など理系的な科目もありますが、独学や講座でしっかり対策すれば問題ありません。
Q2. 独学でも合格できますか?
A. 可能ですが、戦略と継続がカギになります。
一次試験は独学合格者も多いですが、二次試験(記述式)は独学だと苦戦しやすいため、添削指導や勉強会の活用がオススメです。
Q3. 仕事と両立できる?勉強時間はどれくらい必要?
A. 両立は可能。目安は1,000〜1,200時間です。
平日1〜2時間+休日3〜5時間を1〜2年かけて積み重ねる人が多いです。
通勤時間や朝活・スキマ時間の活用が合格のコツ!
Q4. 資格を活かせるのはコンサルだけ?
A. いいえ、企業内でも幅広く活かせます。
たとえば、経営企画・商品開発・マーケティング・管理職など、経営視点が必要なあらゆる部署で力を発揮できます。
実際、企業内診断士の方も多く活躍中です。
迷っている方へ一言
中小企業診断士は、
学びながら実力をつけられる“実務直結型”の資格です。
不安は誰にでもありますが、しっかり情報を集めて、最初の一歩を踏み出してみましょう!
まとめ
中小企業診断士は、単なる資格ではなく、“学び”と“チャンス”が詰まった国家資格です。
取得する過程で、経営の全体像を体系的に学べるだけでなく、
合格後も実践的なスキルや人脈を活かして仕事の幅を広げていける、
とても“育つ資格”です。
思い立った今がチャンスです!
診断士は、勉強すればするほど“自分が変わる”のを実感できる資格です。
キャリアを真剣に考えるすべてのビジネスパーソンにとって、大きな武器になります。
ぜひ一歩を踏み出して、
未来の可能性を広げてみてください!
\それでは/